小説の壁
小説を書き始めて10年が過ぎてしまったが、全国誌からてんで相手にされないのは持って生まれた才能の限界だから仕方がないとして、未だに創作技術上の問題 − それもごく初歩的なものにぶつかって難儀するのには、自分のことながらうんざりする。
現在つっかえているのは、主語の書き方なのである。
誰もがそうではないにせよ、小説を書こうとする多くの人が、最初の何作かは主人公を架空の「私」「僕」「俺」にするものだ。慣れてくると、三人称で書いてみたくなる。筆者の場合、ここで早くも壁に当たった。少し書き進んで読み返したところ、主語(人名および人称代名詞)が多すぎる。要するに「彼は」の洪水だ。
同じ内容の文章を何度も書き直し、やがて頭にきて白紙からやり直そうと決めたとき、名案が浮かんだ。短編だから、章によって「主観(視点)」が移動したりはしない。だったら、とりあえず「私」で書き進め、後から機械的に「私」の文字を三人称に書き換えればよいではないか。ワープロには自動的に特定の文字を置き換える機能も付いているから、存在しない筈の「私」が文中に残ってしまう恐れもない。
不思議なことに、一度この方法を取って以後、最初から三人称で書いても主語が氾濫することはなくなった。結論からいえば、主観の移動がない限り、三人称であることを特に意識する必要はないのである。
その後、ワープロの文書冒頭に「主観転換を伴う三人称小説の試み」などと記した短編
に取り組んだりして、一人称的な部分と三人称的な部分の書き分けを覚え、複数の登場人物の内面に踏み込む技術も身につけた − と自負して、さらに何年も経ってから妙なことになった。
人の名前は姓と名で構成される。不自由なことに、小説にはある種の慣習か伝統みたいなものがあって、女性を姓で呼ばないことになっている。読者として小説に接しているうちは意識しなかったのに、いざ自分で『加藤は裕紀子に言った』などと書いてみると、あれ? なんか変だな − と違和感を覚える。登場人物の設定次第では「名」で統一することも出来るけれど、毎度毎度そうする訳にもいかないのである。
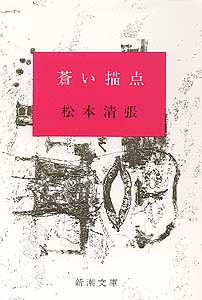 これまで技術的な問題は、既成の小説作品を分析して解決してきた。一時期、通信教育で小説の添削をして貰っていたことがあるけれど、お役人が決めた「当用漢字」だけを使え、という向こうの方針から衝突が生じ(そんなものは憲法の定める「表現の自由」の範疇である。"体言"はなるべく漢字で書かないと無意味な句読点がどうしても多くなり、結果として文章のリズムを損ねる)、しまいには「ここはこう直してくるだろうな」という予測が的中するようになったので、馬鹿馬鹿しくなって辞めている。
これまで技術的な問題は、既成の小説作品を分析して解決してきた。一時期、通信教育で小説の添削をして貰っていたことがあるけれど、お役人が決めた「当用漢字」だけを使え、という向こうの方針から衝突が生じ(そんなものは憲法の定める「表現の自由」の範疇である。"体言"はなるべく漢字で書かないと無意味な句読点がどうしても多くなり、結果として文章のリズムを損ねる)、しまいには「ここはこう直してくるだろうな」という予測が的中するようになったので、馬鹿馬鹿しくなって辞めている。
蔵書の中から参考になりそうなものを漁ってみて、選んだのが松本清張の『蒼い描点』(新潮文庫)。残念ながら純文学では適当なものが思いつかなかった。
『典子は、今度はホームをゆっくり歩きながら、田倉のようすを上から観察した。早く出て彼につかまってはかなわない。場所も箱根で、典子ひとりだから、うるさいことを言いかねないのだ。それと、田倉は誰といっしょに、ここに来たのか、それを見たい興味もあった』
文章の中で双方になるべく距離を置く、というのが解決法であるのは明らかだが、
『それから三十分後には、典子は、白井と竜夫と三人で、三階のがらんとした部屋で話していた。』
のように、近接している箇所もある。全体的には、フル・ネームにしてみたり役職名を使ったりと、意外と著者も苦労しているのかな? という印象が拭えなかった。提示部−これは本来「音楽用語」で、筆者が勝手にフィクションを構想する際に用いているだけだが−では原則としてフル・ネームで、主役格は徐々に男性も「名」に移行、脇役格の男性はフル・ネームと「姓」を、女性はフル・ネームと「名」を使い分けているらしい。
せっかく文芸同人誌に所属しているのだから、合評会でも活用出来るとよいのだけれど、私の見る限り……というより感じる限り、文学の同人誌なんていうのは、どうしても「世に出られない屈折したプライド」のぶつかり合いという側面を有し、技術的な「弱み」を見せられるような場ではないのである。
この問題は、少なくとも書きかけの中編が完成するまで、かなり厄介なものとして尾を引きそうだ。
HOME 最新号へ
バックナンバー目録へ戻る際はウィンドウを閉じて下さい